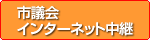|
庄本けんじの代表質問
2025年02月26日
財政見通しと財政構造改善実施計画の推進との関連について次に、財政見通しと財政構造改善実施計画の推進との関連について、お伺いします。 財政構造改善実施計画の策定作業は、まず、素案がしめされ、それに対する意見を公募する、いわゆる、パブリックコメントが実施されました。その結果、素案の内容に、いくつかの修正が加えられました。 そこで、私が注目したのは、修正するするにいたった、その理由です。所管事務報告では、修正の理由には二つある、と述べています。一つは、パブリックコメントで寄せられた意見をふまえた、ということ。二つ目は、収支見通が、「素案公表時点と比較」すると「令和7年1月時点では、令和6年度の歳入で市税や地方交付税の増が見込まれ」たからだ、としています。 同じ報告のなかで、修正の基本方針という項目があります。そこでの説明では、「パブリックコメントや議会の意見、また市税収入等の上振れも考慮し、日常生活への影響が比較的大きいと考えられる福祉サービスの見直しについては、一部見送り等を行う」と述べています。つまり、修正するにあたっては、一つは、「パブリックコメントや議会での意見」、そして、二つには、「市税収入等の上振れ」をふまえる、としているのです。これは、注目すべき、重要な指摘だと思います。 そこで、質問です。 財政構造改善実施計画の策定過程で修正が行われました。今後、計画を推進してゆく過程においても、市民の声を参考にし、計画の修正を行う可能性があるのかどうか、市の見解を、お伺いします。 以上、市長の政治姿勢について質問いたしましたが、それは、物価高騰で苦境に立たされている、市民生活の実態を、政策の起点に置くべきだ、という観点からの質問です。暮らし第一の西宮市政への転換が求められている、ということを強調し、次の質問に移ります。 次の質問では、市政の具体的な問題を、いくつか取り出して質問いたします。 一つは、「阪神西宮駅北地区公民連携事業」、いわゆる、阪神西宮北側開発の問題についてです。ここの質問では、この事業の全体についてではなく、巨大高層マンションを建設することの是非について、お伺いします。 そもそも、タワーマンションにまつわる諸問題は、すでに、いたるところで、数々の問題が指摘されているところです。たとえば、区分所有者の高齢化、富裕層の投資目的による所有、セカンドハウスとしての所有、良好なコミュニティーづくりができず、管理組合の総会や集会の議決が困難になる、場合によっては、修繕工事の合意さえできない、資金不足による適切な修繕もできない、という指摘です。 このような重大な問題を数多く生じさせるタワーマンションの建設を、規制するのではなく、逆に市が関与してすすめようとする、そのようなことが、見過ごされてよいはずがありません。 そこで、質問です。 市は、公民連携と称して、開発事業に関与し、地区計画などのいくつかの制度を活用することで、40階建てにもなる超高層マンションの建設を可能にしようとしていますが、問題だらけのタワーマンションをつくることについて、そもそも市はどのように評価し、それをどのように説明するのか、お答えください。 二つ目は、都市計画道路山口南幹線の道路拡幅事業についです。 この道路拡幅事業は、神戸市域につくられる物流倉庫が新たに開業されることが原因となって交通量が増加する、それに対応するため、と説明されています。新たな物流倉庫の開業がなければ、道路を拡幅する必要はありません。拡幅の必要性を生じさせているのは、物流倉庫の新たな開業にあります。なのに、なぜ、道路拡幅にかかる費用を、原因者である事業者には、負担がおよばず、西宮市の税金が投入されるのか。そこには、論理的な合理性が欠けている、と考えざるを得ません。 そこで、端的にお聞きします。道路拡幅の目的は何か、お答えください。 三つ目の質問は、保育所の待機児童対策についてです。 西宮の保育所の待機児童の現状は、依然として深刻です。昨年の4月、待機児童数が前年比で、65人増の121人でした。この問題を議会で私が取り上げたとき、市長は答弁の冒頭で、謝罪をされました。それほどに、重大な問題なのです。市政の最重要課題と位置付けるべき問題です。 そこで、おお尋ねします。 保育所の待機児童を解消する課題は、市の喫緊の課題であり、最重要課題であるという認識に、いまも変わりはない、と明言できますか、市の認識を聞かせてください。 そのうえで、待機児童対策の目標について、かさねて、お聞きしておきます。政府基準の待機児童をゼロにするという目標は、いうまもなく、いますぐにでも達成すべき課題です。しかし、そもそもの待機児童対策というのは、希望する保育所に入所できない人をゼロにすること、つまり、子どもたち全員が希望する保育所に入所できる、これを目標にすべきなのです。市は、かねてから、そのように明言してきました。この方針は、いまも変わらず持ち続けている、と信じてよろしいでしょうか。お答えください。 四つ目の問題は、教員の多忙化の問題と教員不足の問題についてです。 教員の多忙化の問題は、政治の舞台に登場してから、ずいぶん久しい年月を要しています。しかし、さまざまな取り組みを試してはいるものの、教員の多忙化は、一向に解決できず、むしろ、厳しくなっています。 教員の多忙化は、歴史をさかのぼると、政府が、問題意識をもちはじめたのが1950年代の早い時期でした。研究者たちによれば、1952年には、教員の勤務実態の調査を、当時の文部省が実施しています。この調査で、教員の一日当たりの平均勤務時間が11.3時間との結果が公表されています。その後も、政府による調査は繰り返されてきましたが、超過勤務の実態は、ほとんど変わらず、慢性化しています。それが、2000年代に入ると、一段とひどくなり、精神疾患による欠員が急増するなど、教員の多忙化は、質的な悪化をともなって、すすみました。 こうした教員の超過勤務の状態は、教員不足を引き起こし、担任が配置できないほどの事態になり、その状態が慢性化しつつあります。まさに、いま学校は、重大事態に直面しています。 これを解決するためには、教員の勤務条件そのものを根本的に変える必要があります。そのためには、少なくとも、二つの改革が求められます。一つは、授業の受け持ちのコマ数を減らし、教員定数を増やすこと。もう一つは、教員の残業代ゼロ制度というべき、公立教員給与特別措置法を廃止し、残業代制度を復活させることです。 もちろん、少人数学級をさらにすすめるなど、さまざまな改革が求められます。しかし、教員の多忙化を解決するためには、やはり、教員の勤務条件の抜本的な改革が求められているのです。 そこで、お尋ねします。 教員の多忙化の解消のために、どんな取り組みをされているのか、お答えください。 以上、壇上からの質問を終わります。一連の答弁を得たのちに、再質問、意見要望を述べさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 |
(c) 2002-2025 日本共産党西宮市会議員団
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 TEL:0798-35-3368 FAX:0798-22-7815
※記事の無断転載はご遠慮ください。
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 TEL:0798-35-3368 FAX:0798-22-7815
※記事の無断転載はご遠慮ください。