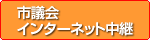|
野口あけみの反対討論
2025年03月25日
議員提出議案第7号 西宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件について議員提出議案第7号 西宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の件について、日本共産党西宮市会議員団は反対します。以下、理由を述べます。 本議案は、現在41名の西宮市議会議員の定数を、1名減じて40名にしようとするものです。 提出者を代表しての維新・渡辺議員の提案説明によれば、 市の財政状況がひっ迫していることを前提に、 ・市当局が財政構造改善の取り組みで、施策・事業見直しでの市民サービスの削減、職員人件費の削抑制と合わせ、職員定員の抑制にも取り組んでおり、当然、二元代表制の一翼である議会としても議員数の適正化=定数削減すべき。 ・また、この間、定数を7名の削減し現在41名だが、過去の一定期間40人で議会を運営してきたことも考慮したとしています。 本議会では1971年に議員定数を44名から48名へと増員して以降、長く48名定員で運営されてきましたが、1999年の地方自治法の改正で、人口区分別に議員定数の上限数が設けられ、その範囲内で各自治体が独自に条例で定めることとなり、本議会の場合は46名が上限でした。2002年12月議会で、定数46名とする案、45名とする案、42名とする案がそれぞれ提案される中、45名と決定。以降、2010年には42名へ、2014年41名と推移、2018年には40名にする提案がありましたが、これは否決され、現在に至っています。 私は、1999年に議員となりこの経過を体験している者ですが、改めて議事録を読み返してみたところ、議員定数を削減すべきとする議員会派と、むしろ議員定数は増やすべきだが少なくとも現状維持とすべきとする議員会派で、主張は折り合わず、最終的には多数決で決めてきたのです。 その論点もそれぞれ現在に至るまで大筋で共通しています。先ほどの質疑でもそれは同様であったと思います。 すなわち、削減派は、その時々の財政状況をとらえ、これはいつでも財政状況は厳しいという前提になっていますが、議員数の削減をもって財政に寄与するとしている。一方、維持派は、財政問題を言うなら、議員待遇の見直しを進め議員一人当たりの経費削減でもって財政に寄与することはできるとしてきました。 また、削減派は議員を減らすことによって議会の効率化をすすめ、機動力を上げる、今回も意見集約がしやすくなると説明していました。という主張をし、維持派の議会に多様な市民の意見を反映させることが重要であり、民主主義には時間がかかることもあるという主張と対立してきたのであります。 この期間はまた、全国的にも議会改革をめぐってさまざま議論が交わされてきた期間でもありました。議会基本条例が策定され、議会活性化のための方策がとられ、議員の待遇についても時間はかかりましたが、タクシーチケットなど、いわゆる優遇とされるような施策は是正されてきたのも事実です。今議会では、委員会の正副委員長報酬加算が廃止されました。ただ、まだ中核市のなかでも報酬が高い、政務活動費が高いなどの課題は残されています。 すこし話はそれましたが、ともあれ執行機関である市長と議事機関である議会という、住民から直接選挙で選ばれた二つの機関で地方自治体は構成されています。この二元代表制における議会は、なにより執行機関の監視、チェックという重大な役割があります。財政が厳しいため行政が職員を減らすから、二元代表制の一翼である議会も減らすなどという議論は違和感以外ありません。委員会で質したところ、財政危機を招いたのには予算等に賛成してきた議会にも責任がある、痛み分けなどという主張もありました。 この間、行政課題はますます増加し、多様化しています。職員定員を減らし、非正規職員にその職務を担わせ、さらに業務委託や指定管理者制度など本来行政が担うべき事業施策を外部に任せているからこそ、そこを含めて議会は厳しくチェックしなければなりません。この基本的観点から議員定数を考えるべきです。議員を選ぶ市民の意見や要望も多様化しています。その多様性を十二分に反映させる議会が必要です。その点からも議員定数は減らすべきではありません。 以上、反対討論といたします。 |
(c) 2002-2025 日本共産党西宮市会議員団
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 TEL:0798-35-3368 FAX:0798-22-7815
※記事の無断転載はご遠慮ください。
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 TEL:0798-35-3368 FAX:0798-22-7815
※記事の無断転載はご遠慮ください。