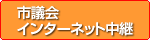|
庄本けんじの一般質問
2025年09月04日
先の参議院選挙で問題となった排外主義について、市長と教育長の見解をお伺いいたしますみなさん、おはようございます。日本共産党の庄本けんじです。傍聴に来られたみなさん、また、インターネットや、さくらFMでご視聴のみなさん、ありがとうございます。ただいまより、日本共産党西宮市会議員団を代表して一般質問をおこないます。 まず、先の参議院選挙で問題となった排外主義について、市長と教育長の見解をお伺いいたします。 7月3日公示、7月20日投開票でおこなわれた第27回参議院通常選挙は、外国人の排斥を競い合うというこれまでの選挙ではありえなかった、異常きわまりない選挙戦が、一部とはいえ大々的に展開されました。演説などで、「外国人が優遇されている」、「外国人の犯罪が増えて治安が悪化している」などと、まったく根拠のないデマが繰り返されました。しかも、その繰り返しは、暴言を発したその後に、撤回し、謝罪しながら、同じような暴言をまた繰り返す、悪質極まりない暴言の繰り返しでした。このように、このたびの国政選挙は、歴史上かつて経験したことのない異常な選挙戦が持ち込まれた選挙でした。 しかし、一方で、「さすがに、これは放置できない」、「絶対に、許してはならない」という声が沸き起こり、人権擁護の力強い流れが、この日本社会にも存在している、ということをしっかりとしめすことにもなりました。 たとえば、人権問題にとりくむNGOの諸団体が、選挙公示後の7月8日、「参議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対する緊急共同声明」を発出して、「ヘイトスピーチ、とりわけ排外主義の煽動は、外国人・外国ルーツの人々を苦しめ、異なる国籍・民族間の対立を煽り、共生社会を破壊し、さらには戦争への地ならしとなる」と警告し、排外主義の煽動を厳しく批判しました。 この共同声明は、8団体が呼びかけたものですが、賛同団体は、最終、1,159団体にまでひろがりました。 日本ペンクラブは、選挙戦の終盤、7月15日、緊急の声明を発表し、「少しずつでも、成熟し前進してきた民主主義社会が、一部の政治家によるいっときの歓心を買うための『デマ』や『差別的発言』によって、後退し崩壊してゆくことを、私たちは決して許しません」と述べて、排外主義とのたたかいを宣言しました。 全国知事会は、選挙直後の7月23日、24日の両日にわたって開催された全国知事会議で「青森宣言」を発出しています。そこでは、「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す」との当初の原案にはなかった文言を急遽入れ込んで、「民主政治を脅かす不確かで根拠のない情報から国民を守り、国民が正しい情報に基づいて政治に参画できるシステムの構築を求めていく」と述べました。 芦屋市長も、排外主義にたいする見解を、投票箱が閉まったその直後にⅩ(旧ツイッター)で表明し、こう述べています。「市長は、あらゆる市民の暮らしを守るのが仕事です。どんな人でも、一人の市民として人権を守る。だから、差別や排外主義にはNOを突きつけたい」と、きっぱりとした決意をしめされました。 さらに、加えて紹介しますと、弁護士、作家、音楽プロデューサー、DJ、ピースボート共同代表など、各界有志の12人が、7月28日、国会内で記者会見を開き、「デマと差別が蔓延する社会を許しません」とのアピールを発表しました。このアピールでは「私たちは、日本社会に外国人、海外にルーツがある人々を敵視する排外主義が拡大していることに強く憂慮する」と指摘し、「民主主義が壊され、自由が奪われ、戦争への道に進んでいくことを私たちは許しません」と決意を述べるとともに、「多くの市民のみなさんが、人権と民主主義社会を守るために立ち上がることを呼びかけます」と結んでいます。 そこで、石井市長に、伺います。 私は、排外主義にもとづくさまざまな差別発言は、国民のあいだにひろがる不満や感情を、時代逆行の方向へ掻き立てる意図をもって誘導するものでしかない、と受け止めています。そして、それは、究極的には破綻せざるを得ないものではありますが、たたかわずして放置すれば、社会全体に染みのように広がり、いったん攻撃相手と見定めれば、その攻撃対象をいかような方法で抹殺しても平気という、かつての暗黒社会に後戻りすることになる、と警告せざるを得ません。 外国人を的にして嘘とデマによって攻撃をする、そのような排外主義を、許すわけにはいきません。 市長自身の見解を聞かせてください。よろしくお願いします。 あわせて、教育長にもお聞きします。 西宮市には、約90の国籍、約9000人近くの外国市民が生活しています。学校や幼稚園にも、外国籍や日本国外にルーツをもつ幼児、児童、生徒が、ともに生活しています。すでに、多文化共生はすすんでいます。 西宮市は、多文化共生のため、日本語指導が必要となる児童生徒への支援強化、やさしい日本語の使用、多言語対応の文書発行、地域住民やNPOと連携した支援など、さまざまな取り組みがされています。 排外主義にもとづいた差別や偏見を、 子どもたちの間に浸透させてはなりません。 教育長の見解を、聞かせてください。 次に、学校給食調理場の熱中症対策についてお尋ねします。 猛暑日が常態化しています。熱中症で倒れる人が増え、昨年、2024年(令和6年)、5月から9月のあいだの熱中症による救急搬送は97,578件にのぼり、熱中症による死亡者は、全国で2,152人にもなりました。 職場も同じように深刻な状態にあり、職場の熱中症による死傷者数は全国で1,106人、そのうち死亡者は31人でした。西宮市の学校でも、この7月に、二つの学校で、学校給食調理員が救急搬送されました。 そこで、当局にお聞きします。 第一は、国の労働安全衛生規則の改定にもとづく学校給食調理場における新たな熱中症対策についてです。 熱中症対策には、予防のための対策と熱中症が発生したときの緊急的対応との二つの対応があります。このたびの労働安全衛生規則の改定では、予防対策の強化をもとめるとともに、熱中症が発生したときの対応について、新たな規定を設け、それを義務化しました。いわゆる熱中症対策の義務化です。この規定は、ことしの6月1日から施行されています。 教育委員会は、労働安全衛生規則の改定を受けて、学校給食調理場における新たな熱中症対策について、義務化の対策と、予防対策のそれぞれについて、どのように対応をされたのか、お答えください。 第二に、二つの学校で給食調理員が熱中症で救急搬送されましたが、その概要と検証について、お聞きします。その際、熱中症対策の「義務化」に照らしてどうだったのか、また、予防対策の観点ではどうだったのか、問題点があるとすれば、それはいったい何だったのか、現時点での結論をお答えください。 第三に、給食調理場への空調設備の全校整備について伺います。 調理場への空調設備の設置については、このたび、新たに予算を立て、これまでの設置計画を前倒しして実施するとの方針がしめされました。 そもそも、給食室への空調設備の設置は、そこで働く人の熱中症対策として重要なだけでなく、安全な給食を児童生徒に提供するための食料安全衛生管理のうえからも、必要なこととされているところです。国の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、施設整備の管理の項目のひとつに、「高温多湿を避けること」、そのためには「調理場は湿度80%以下、温度は25度以下に保つことが望ましい」と明記されています。 にもかかわらず、これまでの市の整備計画では、全校設置の完了が、2031年度(令和13年)末になるとのことでした。これはあまりにも遅すぎるという当然の声が上がり、計画の大幅な短縮を求める声が、職場からも、議会からもあがりました。私たちも強く要求してきたところです。ですから、整備計画を前倒しすることについては、大歓迎、大賛成です。 しかし、この要求は、あまりにも切実で切羽詰まった要求だったものだけに、計画を見直したその理由については、しっかりと聞かせていただきたいと思うところです。従来の計画を見直すことになったその主な理由について、お聞かせください。 第四に、今後の熱中症対策の強化についてお聞きします。 空調設備が設置されれば、調理場の安全環境は、大きく改善されます。しかし、設置完了までのあいだの今後の熱中症対策については、給食調理の職員が救急搬送された事態を重く受け止めるとするならば、なんらかの改善が必要になると考えます。どのような強化策をお考えか、当局の対応について、お聞きします。お答えください。 以上で、壇上からの質問を終わります。答弁を受けた後、自席にて、再質問、意見、要望を申します。ご清聴ありがとうございました。 以上 |
(c) 2002-2025 日本共産党西宮市会議員団
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 TEL:0798-35-3368 FAX:0798-22-7815
※記事の無断転載はご遠慮ください。
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 TEL:0798-35-3368 FAX:0798-22-7815
※記事の無断転載はご遠慮ください。